※2013年長男出産時にfacebookのノートに書き留めていたものに追記して転載します。
妊娠発覚〜出産後の補助費払い戻しまで、
せっかくなので残しておきます。
※実質、公立の病院で何事もなく健康に産んだら、出産費用はほとんどかからない!むしろ返ってくるくらいです♪

Contents
はじめに
長男の妊娠発覚時、色々とバタバタとしていてまだ住所が実家にありました。
その後、婚姻届を出した時に住所は旦那の実家の住所になったけれど、一時的に住んでいた場所の病院で出産するという、稀有な状況に。笑
つまり、
母子手帳(現住所登録のある場所でもらう)は実家のS県H市
妊婦健診補助券は入籍後に住所を移した旦那の実家のA県A市
最終的に健診&出産に通った病院は一時的に住んでいるM県K市だった。
妊婦健診費用は、全額実費で支払い、のちに補助券をもらったA県A市に領収書を持っていき払い戻し請求の申請をしました。
母子手帳をもらう
病院選び!
・妊婦健診や出産費用は病院によってかなりの差があります。
(妊婦健診はできるが、お産は別の病院でお願いします。ってところもあるので確認が必要。あと婦人科のみとか。私はそれで初診料3件払いました…)
初回検査
・第一回の初回検査(8〜10週目くらい)も、病院によって負担額が違うのでいくつかの病院に電話してもいいかも。8,000円〜12,000円くらいかかります。
母子手帳と一緒に検診補助券をもらうまでは、保険がきかないのです!!
(※妊娠は病気じゃない。)
・生理が遅れて妊娠検査薬を使い、陽性が出て5・6週目くらいで病院に行っても「赤ちゃんの袋が確認できない。赤ちゃんの心拍が確認できない。また2週間後に来てください。」と言われることが多く、実費での検査を何回かする検診費用を抑えたい場合は8〜10週くらいまで待って検診を受けた方がいいかも。
でも、陽性が出ると、気になってしまうもの。
裏技としては、「妊娠の可能性がある」と病院にかかるのではなく、「お腹が痛い」「生理不順」「おりものに違和感がある」と言って婦人科にかかると、保険がききます。
妊娠証明書
・市役所などに母子手帳をもらうには<妊娠証明書>を書いてもらう必要があります。病院で胎嚢と心拍が確認できて初めて妊娠が確認されます。
※心拍や胎嚢が確認されない場合、自然流産や子宮外妊娠の可能性もある為。
(→子宮外妊娠の疑いで入院・自然流産の経験もあるのでまた書きます。)
・証明書発行料も病院によって違います!(一回3,000〜10,000円程度)
・母子手帳は住所のある場所でしかもらえないです!授かり婚や事実婚などでまだ住所変更をしていない場合は注意。
・その後住所を移しても、母子手帳は変更されないが、補助券は住所地でもらいなおす必要があります。
※私の場合、母子手帳は実家のS県H市、補助券は入籍後に住所を移したA県A市、病院は住んでいるM県K市だったw ややこしい。
検診費用と出産費用は別物。
★妊婦健診代 実費 86,300円 (公立病院)
※住所のある自治体で補助券がもらえ、その地域で使用できる。オーバーした分だけ、自分で支払う。 補助額は自治体によって違うし、病院によっても健診代が違うので確認が必要。
※里帰り出産等で住所がある場所以外で健診を受けた場合、一時的に自分で負担してあとから自治体に請求することができる。
★出産費用 424,678円 (公立病院)
(内訳:入院料130,540円、分娩料180,000円、新生児管理保育料64,000円、産科医療補償制度30,000円、検査・薬剤等11,850円、処置・手当等1,350円、その他6,938円)
→出産育児一時金(42万)によって、実質負担額4,678円
※市立病院で正常分娩(会陰切開、抗生物質点滴あり)、5日入院。
※先に確認したときは、ほぼ42万で収まりますとのこと。
※医療機関直接支払制度が適用されて、退院するときに4,678円を払うのみでした。
※適用外の医療機関の場合は、退院時に出産費用を立て替え、後日2年以内に申請すれば戻ってくる。
※42万以内だった場合は、申請すれば差額がもらえる。
返金請求
妊婦健診の補助券と、実際に支払った領収書を照らし合わせて、払い戻しの請求をしました。
・市が違っても、同じ県内であったり、病院と自治体が提携してもらうことができれば補助券を使うことができるようですが、今回はできませんでした。
・1年以内に請求するなど、地方自治体によって期限が決まっています。
全額返還されるわけではない。
・補助券は内容が記載されており、その都度で金額が違います。
受けられる検査などの内容が若干違ったり、順番が違ったりするので、全額をそのまま返還してもらえる訳ではありませんでした。
・移動の都合で受診できないこともあったので、2回分の検査を1日でまとめてやってもらうこともありました。その場合は、領主書を2回分として分けて発行してもらいました。
・返還請求したA市では、日程を入れ替えたりして、なるべく支払った金額と補助券が合うように調整してくれましたが…返還されたのは、68310円でした。
結果:健診代は17,990円の負担でした。
◎出産育児一時金とは?
妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。 まとまった支出の経済的負担の 軽減を図るために支給されるものが、「出産育児一時金」です。
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円)出産育児一時金が支給されます。出産一時金は国保・社保関係なく健康保険に加入していれば支給されます。
◎産科医療補償制度とは?
分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
※7か月くらいの健診の時に、別室に呼び出されて説明がありました。書類に目を通してサインして。制度を利用するためには30,000円がかかるが出産育児一時金を適用できるので、退院時に精算される。
◎出産手当金とは?
仕事をしているママは、出産に備え当分の間(産前42日・産後56日)仕事を休まなければなりません。ですが、産休中や育児休暇中は給料がでない会社がほとんどです。その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。出産手当金は加入している健康保険から支給されます。正社員でなくてもパートやアルバイトでも健康保険に加入していて産休中も健康保険料を払っていれば出産手当金をもらうことが出来ます。(産休後、仕事に復帰するママが対象となります。)
※私も旦那もまともな仕事をしていなかったのでもらえず…otz
◎妊婦健診の補助券とは?
各自治体から出される妊婦健康診査の補助券。母子手帳といっしょに14回分(私がもらったものは歯科検診や産後、乳児健診の分もついていた)もらって、毎回病院で使うもの。それぞれ限度額が決まっており、その額が自治体によってさまざま。里帰りの場合は、同じ分だけあとから請求することができる。
 気仙沼でSLOWな子育て by MISATOSUGIURA
気仙沼でSLOWな子育て by MISATOSUGIURA

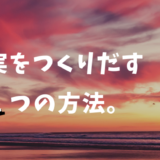
コメントを残す